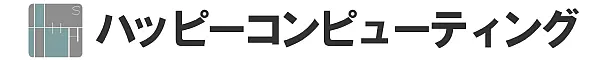RubyのMatzさんが2年ほど前に「ちょっと待った!小中学校でのプログラミング教育 」という記事の中で3つの課題を挙げています。
- 誰が教えるのか
- どのように評価するのか
- 何を教えるのか
この課題について私なりに回答を出すことで、ハッピーコンピューティングの指針としたいと思います。
誰が教えるのか
ハッピーコンピューティングで教えるのは私です。
システムエンジニア歴10年程。
Matzさんはこうも言っています。
「教える人はプログラミングの楽しさを自覚している人でなければ成果をあげられないと思います」
「プログラミングの能力は、創造性をともなうという点である種芸術に似ています。」
芸術系の大学を出ていますので、Matzさんのご意見からして適任と判断されうると自負しています。
プログラミングのジャンルは広く、場合によっては私の経験が不足する場面もあると思います。
ですから、ハッピーコンピューティングは、基本的に自学自習です。
私は教える先生ではなく、ある程度経験がある先輩です。
生徒さんが勉強する内容を私も勉強し、そばでサポートする人です。
どのように評価するのか
ハッピーコンピューティングでは成果を発表する場を設けようと思っています。
発表を聞く人の感想がそのまま評価になります。
学校教育における音楽や家庭科、保健などの科目も、評価が難しいものと思います。プログラミングも同様です。
ハッピーコンピューティングは学校ではなく、ピアノ教室などの習い事と同じ位置づけです。
たとえば私の娘が通うピアノ教室では、年に一度発表の場を設けていますので、ハッピーコンピューティングもそれに倣おうと思います。
何を教えるのか
プログラミングの楽しさを伝えるためには、できるだけコンピュータを使いたいように使わせてあげるのがいいと思います。それが一見役に立たなそうでも。
たとえば私は、使ったことのないオペレーションシステム(OS)をパソコンにインストールするのが楽しかったのです。
もう15年以上も前ですがひとつのOSを1日に7回もインストールにチャレンジして失敗しまくってたこともありました。
あまり賢くなかったから原因を探ろうとかしなくて、闇雲にさっきはこうやって失敗したから今度はこうとか、そういうでたらめな経験が妙に楽しかったのです。
あるOSをThinkpadというノートパソコンに入れようとして失敗して、原因がわからず途方に暮れそうになってた時に、なぜか以前に買い込んでいた本を熟読したら「このOSをThinkpadに入れるときはこうする」とハッキリ解決策が載っていて喜びのあまり叫んだとか、
どんどんマイナーなOSに走ってったとか、
リアルタイムOSという種類の、パソコン向きでないOSをパソコンにインストールしたとか、
有益なアプリケーションで何をするでもなく、ただただOSのインストールだけで楽しいと思える、それが私であり、それなりにソフトウェア開発の現場でもお仕事を続けることができました。
パソコンを占有して自由にできる環境でないとそういう体験はできないと思いますので、ハッピーコンピューティングでは、ひとり一台専用のパソコンを貸し出します。
システムを壊してもリカバリすればいい。
誰にも迷惑をかけないから大胆なことも試すことができる。
そういう環境で、できるだけ興味を持つことを教えます。
私のように、使ったことのないOSが動いた!というだけで喜びを感じる個性的な生徒は、ひょっとしたらプログラミングはあまりしないかもしれません。
それはそれでよしと思います。
コンピュータへの興味を深め、使いこなすことを楽しいと感じるようになれば、やがて自然にプログラミングを経験することになると思います。
ハッピーコンピューティングでは、何よりもこの「興味」「楽しさ」を大切に伝えます。