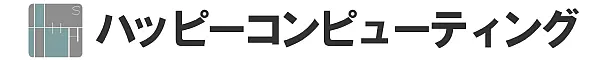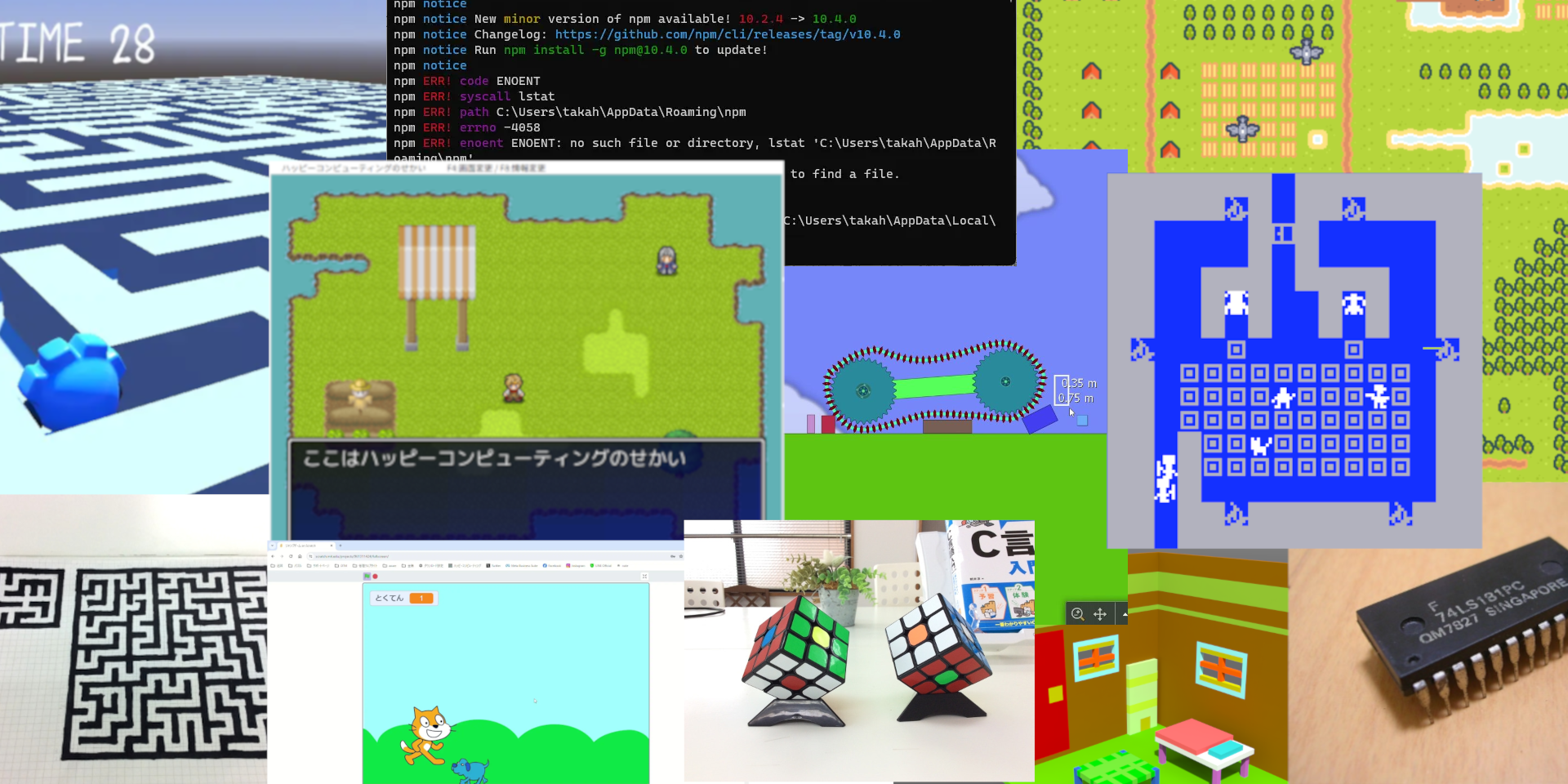ハッピーコンピューティングの指導方針をまとめます。
市販の書籍で学ぼう
ハッピーコンピューティングには独自のテキストがありません。各自好きな本で学びます。
パソコンやプログラミングに関する書籍はすでに多数出版されています。探せば必ず自分にあった本に出会えます。
ハッピーコンピューティングとしてもそれぞれの知識や技術レベルを考慮して、興味や関心の相談にのったり、おススメの本を紹介したりします。
1冊学び終えたらまた次の本、それが終わったらまた次。ぜひ自宅の本棚に技術書が増えていくのを楽しんでください。
画一的で同じような表紙、背表紙のテキストを並べるよりも、書店で眺めるような本棚を作りましょう。
コンピュータの前に座っているだけが学びではありません。
書店に通い、コンピュータ関連の本棚の前で立ち止まる。背表紙を眺め、専門用語や単語を知る。これも立派な勉強です。
スクールや教室で他人から「教わる」のではなく、世間一般の本から自主的に「学ぶ」ことを身につける。それはとても大切なことと思います。
楽しさを知ろう
ハッピーコンピューティングはコンピュータを操る楽しさを伝えます。
技術や知識を身につけたいなら継続的に学び続けることが一番大切。だけどつまらないことは続けられません。それが楽しいと思えてこそ、継続的に取り組むことができるでしょう。
優秀なプログラマはたいていプログラミングが好きです。プログラミングは嫌いだけどプログラマとして優秀という人はあまり見かけません。コンピュータを操る楽しさに気づけば、きっとプログラミングも好きになれるでしょう。
コンピュータを操って素敵なものを作ったり、生活を便利にしたりするのも、すべてこの楽しさがベースにあってこそです。
楽しいから、好きだから、のめりこむように未来を作っていける。そんな道に子どもたちを導いてまいりたいと思っています。
コンピュータの可能性に気付こう
好きだ好きだと言ってもゲームにしか興味が持てないようではもったいないです。
コンピュータはただのゲーム機ではありません。もっとたくさんのことができる、大きな可能性のある機械です。
絵が描ける。音楽を奏でられる。リアルな3Dモデルも作れるし、アニメーションも、もちろんゲームも作れます。
撮影したものを編集したり、天気を予想したり、複雑な計算をまかせたり、本が書けたり。
インターネットを通じて、調べものができたり、楽しい動画を見たり、買い物ができたり。
メールも、ラインも、SNSも。いまや人工知能で人間のように会話できたり、自身のかわりに歌を歌わせたり。
全部コンピュータがあってこそです。
いやいや、もっともっと。
今はまだ想像すらできないことだってできるようになる・・・かもしれない。
そんな可能性を秘めた機械。それがコンピュータです。
ハッピーコンピューティングではプログラミングだけでなく、音楽を作ってみたり、ストップモーションアニメーションを撮影してみたり、3Dモデリングに挑戦したり、さまざまな取り組みを通じて、コンピュータの可能性に触れてもらいます。
将来につなげよう
専門的にコンピュータのことを学ぶのであれば、やはり専門の大学や専門学校に進学することをお勧めします。
ハッピーコンピューティングは、そうしたコンピュータを専門的に学べる大学や専門学校へ進学した時につまづかないように、その下地を作ります。
コンピュータに興味を持ってもらう。コンピュータのことを好きになってもらう。
そこからスタートして、実際にプログラミングしてみる。CGを作ってみる。音楽を奏でてみる。
大学生や専門学校生になった時に、とてもスムーズにスタートが切れるように、また、志半ばで夢をあきらめないために、コンピュータと付き合っていくための基礎体力のようなものを養ってもらいます。
ハッピーコンピューティングは2015年の立ち上げ以来、10年間で実際に、専門的な大学に進学した生徒さんや、大学を卒業してコンピュータ開発の会社に就職した人材を輩出しました。
より専門的な使いこなしや、自身の力でコンピュータに取り組んでいけるような未来に、子どもたちを導いてまいります。
効率よく稼ぐのはあとまわし
コンピュータを駆使して、若くして大金持ちになった人を見ることがあるでしょう。それはとても効率よく稼いだように見えます。
将来の安定のためとか、効率よくお金を稼ぐために私もコンピュータを学ぼうというのはかまいませんが、あまり理想的ではないと思います。それではコンピュータを学ぶ意欲を維持するには力が弱いでしょう。
コンピュータは現在までの人類の知の結晶であり、奥が深いものです。深くコンピュータを知るには、その楽しさや可能性に根差した「もっと知りたい」と思えるような強い気持ちがあったほうがいいと思います。
効率よくお金を稼ぐため、というのはいったんあとまわしにしましょう。お金は、本気で学んだ人に結果としてついてくるものです。
これはコンピュータ科学だけでなく、どの分野においても言えることだと思います。